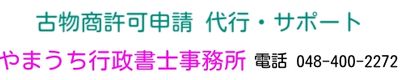建設業許可の要件(条件)をわかりやすく解説
建設業許可を受けるための6つの要件
建設業許可を受けるための要件は以下の6つです。
- 要件① 経営業務の管理責任者等がいること
- 要件② 適切な社会保険に加入していること
- 要件③ 専任の技術者が営業所ごとにいること
- 要件④ 請負契約に関して誠実性があること
- 要件⑤ 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 要件⑥ 欠格要件等に該当しないこと
これら6つの要件をすべて満たしていないと建設業許可を受けることができません。
次にそれぞれの要件について解説していきます。
要件① 経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
この要件をクリアするためには、以下の「1.常勤役員等個人の経営経験」を満たすか、「2.常勤役員等を含む社員グループ単位の経営経験」の要件を満たす必要があります。
1.常勤役員等個人の経営経験
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人の場合はその役員のうち常勤であるもの、個人の場合は本人または支配人をいう。以下同じ)のうち1人が、次の㋐~㋒のいずれかに該当する者であること
- ㋐建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ)5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ㋑建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- ㋒建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
2.常勤役員等を含む社員グループ単位の経営経験
許可を受けようとする者の常勤役員等のうち1人が、次の㋐または㋑に該当する者であり、かつ、次の㋒~㋓の経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること
<常勤役員等個人の要件>(いずれかに該当)
- ㋐建設業で2年以上の役員等の経験+建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験→あわせて5年以上
- ㋑役員等の経験(建設業以外も可)+建設業で2年以上の役員等の経験+→あわせて5年以上
かつ
<常勤役員等を補佐する者の要件>
- ㋒当該事業者における5年以上の財務管理の経験
- ㋓当該事業者における5年以上の労務管理の経験
- ㋔当該事業者における5年以上の運営管理の経験
- 経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
- 経営業務の管理責任者について更に詳しく知りたい場合には、「経営業務の管理責任者について詳しく解説 」をご覧ください。
要件② 適切な社会保険に加入していること
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(雇用保険、医療保険、厚生年金保険)に加入していなければなりません。事業所の形態、労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険が異なります。適切な社会保険についての基本的な考え方は、以下のとおりです。
<雇用保険>
次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
- ㋐31日以上引き続き雇用することが見込まれる
- ㋑1週間の所定労働時間が20時間以上である
※法人の役員や個人事業主は加入できません。
<医療保険>
法人→労働者数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入します。
個人→常用労働者が5人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できません。
法人・個人の共通事項
・ア 被保険者になるのは75歳未満の者
・イ 国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている場合は、加入しているものとして扱う
<厚生年金保険>
法人→労働者数にかかわらず、加入が必要。
※役員しかいない場合も加入します。
個人→常用労働者が5人以上いる場合に限り、加入が必要。
※事業主本人は加入できません。
法人・個人の共通事項
・被保険者になるのは70歳未満の者
<適切な社会保険の範囲>(下表をクリックすると拡大します)
- 個々の制度の詳細は、ハローワーク、健康保険組合、国民健康保険組合、年金事務所にお尋ねください。
- 社会保険について更に詳しく知りたい場合には、「建設業の社会保険についてわかりやすく解説 」をご覧ください。
要件③ 専任の技術者が営業所ごとにいること
建設工事に関する請負契約を適正に締結し、その履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。そのため、許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、一定の資格や経験を有する者(専任技術者)を配置することが求められています。専任技術者は「各営業所ごと(本社・支社それぞれ)に専属」「常勤」で、かつ「許可を受けようとする業種ごと」に必要です。求められる専任技術者の要件(資格や経験)は一般建設業許可を受けるか、特定建設業許可を受けるかで異なります。ここでは一般建設業許可を受けようとする場合について解説します。
<一般建設業許可を受けようとする場合の専任技術者の要件>
次の①~③のいずれかに該当することが求められます。
①許可を受けようとする業種の指定学科を修めて高等学校もしくは専修学校の専門課程を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、又は許可を受けようとする業種の指定学科を修めて大学、高等専門学校もしくは専修学校の専門課程(専門士又は高度専門士を称する者に限る)を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
※指定学科一覧へ(国土交通省ウェブサイト)
②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者(2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要。期間を重複することはできない)
③許可を受けようとする業種についての国家資格等(土木施工管理技士、建築士、技能士等)を有する者(実務経験も必要となる場合があります)
※営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧へ(国土交通省ウェブサイト)
- 同一営業所内において2業種以上の専任技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
- 経営業務管理責任者と専任技術者は、それぞれの要件を満たすことができるのてあれば、兼ねることができます(同一の営業所内に限る)。
- 経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は、許可の取消の対象等になるので注意が必要です。
- 専任技術者について更に詳しく知りたい場合には、「専任技術者とは?」をご覧ください。
要件④ 請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
なお、ここでの「不正な行為」「不誠実な行為」とは次のような行為をいいます。
- 「不正な行為」→請負契約の締結または履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
- 「不誠実な行為」→工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
- 他にも、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさない者として扱われます。
要件⑤ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業を営むには工事着工費用等が必要になりますので、ある程度の資金を確保していなければなりません。求められる財産的基礎・金銭的信用は一般建設業許可を受けるか、特定建設業許可を受けるかで異なります。ここでは一般建設業許可を受けようとする場合について解説します。
<一般建設業許可を受けようとする場合の財産的基礎等>
倒産することが明白である場合を除き、申請時において次の①~③のいずれかに該当することが求められます。
①自己資本の額が500万円以上であること
→「自己資本」とは、法人の場合「賃借対照表における純資産合計の額」を、個人の場合「賃借対照表における期首資本+事業主借勘定+事業 主利益-事業主貸勘定+利益保留性の引当金・準備金」をいいます。
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
→取引金融機関から500円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいいます。
③許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること(更新申請の場合のみ)
- 更に詳しく財産的基礎等について知りたい場合には、「建設業許可は500万円ないと取れない?」もご覧ください。
要件⑥ 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
(1) 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
(2) 法人である場合は、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人である場合はその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
イ 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
オ 請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規則法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合および結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律の罪
ク 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。