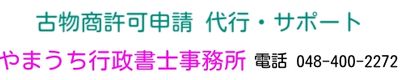板金工事業の建設業許可の取り方【工事内容・条件・資格を解説】
本記事では「板金工事業」の建設業許可を取りたい事業者様に向けて、【工事内容】【許可を取るための条件・資格】【申請手続き】についてわかりやすく解説します。
「板金工事業」とは
「板金工事業」の建設業許可を取るに当たり、まずは、許可を取りたい建設工事が「板金工事業」に該当するのか確認が必要です。
「板金工事業」に該当する建設工事の種類は「板金工事」です。具体的には以下の工事内容です。
- 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
具体例は以下のとおりです。
〇板金加工取付け工事
〇建築板金工事<※1>
<※1>「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。
注)「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。
「板金工事業」の建設業許可を取るための6つの条件
「板金工事業」の建設業許可を取るためには以下の6つの条件全てを満たしている必要があります。
- 条件① 経営能力がある
- 条件② 専任技術者がいる
- 条件③ 財産的基礎がある
- 条件④ 適切な社会保険に加入している
- 条件⑤ 請負契約に関して誠実性がある
- 条件⑥ 欠格要件等に該当しない
次にそれぞれの条件について解説していきます。
条件① 経営能力がある
法人の場合は常勤役員のうち1人以上に、個人の場合はその個人事業主に以下の経験が必要です。
◎建設業を営む会社の役員、又は個人事業主としての5年以上の経験
この経験があることの証明に以下の書類が必要です。
・建設業許可がある法人での役員経験⇒①履歴事項全部証明書+②建設業許可通知書の写し 等
・建設業許可がない法人での役員経験⇒①履歴事項全部証明書+②工事請負契約書or注文書+対応する通帳or請求書+対応する通帳 等
・建設業許可がある業者での個人事業主経験⇒①確定申告書控+②建設業許可通知書の写し 等
・建設業許可がない業者での個人事業主経験⇒①確定申告書控+②工事請負契約書or注文書+対応する通帳or請求書+対応する通帳 等
他にも要件を満たす方法はありますが、認められないケースも多く、難易度が高いです。
経営業務の管理責任者について更に詳しく知りたい方は「経営業務の管理責任者について詳しく解説」をご覧ください。
条件② 専任技術者がいる
営業所ごとに常勤の専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者の要件は、一般建設業許可を取るのか特定建設業許可を取るのかによって違います。
以下にそれぞれの場合に分けて解説します。(一般と特定の違いについて知りたい方は「特定建設業許可と一般建設業許可の違いをわかりやすく解説 」をご覧ください)
<一般建設業許可の場合>
次の1~3のいずれかに該当する者は、一般建設業許可における「板金工事業」の専任技術者になることができます。
1.「板金工事業」の専任技術者になり得る資格を持っている
2.大学の指定学科を卒業+「板金工事」に関する3年以上の実務経験がある 又は 高校の指定学科を卒業+「板金工事」に関する5年以上の実務経験がある
3.「板金工事」に関する10年以上の実務経験がある
以下にそれぞれの要件について解説していきます。
1.「板金工事業」の専任技術者になり得る以下の資格を持っている(実務経験も必要となる場合があります)
| 資格区分 | 資格 |
| 技術検定 | 一級建築施工管理技士 |
| ニ級建築施工管理技士(仕上げ) | |
| 技能検定 | 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) ※等級区分が二級のものは、合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要する |
| 工場板金 ※等級区分が二級のものは、合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要する |
|
| 板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」) ※等級区分が二級のものは、合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要する |
|
| 板金・板金工・打ち出し板金 ※等級区分が二級のものは、合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要する |
・資格があることの証明に資格証明書が必要です。
2.大学の指定学科を卒業+「板金工事」に関する3年以上の実務経験がある
又は 高校の指定学科を卒業+「板金工事」に関する5年以上の実務経験がある
「板金工事業」の指定学科は、以下のとおりです。
〇建築学
〇機械工学
この要件を満たしていることの証明に以下の書類が必要です。
・「板金工事業」の建設業許可業者での実務経験がある⇒①卒業証書+②厚生年金被保険者記録照会回答票+③建設業許可通知書の写し 等
・「板金工事業」の建設業許可がない業者での実務経験がある⇒①卒業証書+②厚生年金被保険者記録照会回答票+③工事請負契約書or注文書+対応する通帳or請求書+対応する通帳 等
3.「板金工事」に関する10年以上の実務経験がある
この要件を満たしていることの証明に以下の書類が必要です。
・「板金工事業」の建設業許可業者での実務経験がある⇒①厚生年金被保険者記録照会回答票+②建設業許可通知書の写し 等
・「板金工事業」の建設業許可がない業者での実務経験がある⇒①厚生年金被保険者記録照会回答票+②工事請負契約書or注文書+対応する通帳or請求書+対応する通帳 等
<特定建設業許可の場合>
次の1、2のいずれかに該当する者は、特定建設業における「板金工事業」の専任技術者になることができます。
1.「板金工事業」の専任技術者(特定建設業)になり得る資格を持っている
2.一般建設業の専任技術者要件に該当+元請としての4,500万円以上の「板金工事」について2年以上指導監督的な実務経験がある
以下にそれぞれの要件について解説していきます。
1.「板金工事業」の専任技術者(特定建設業)になり得る以下の資格を持っている
| 資格区分 | 資格 |
| 技術検定 | 一級建築施工管理技士 |
・資格があることの証明に資格証明書が必要です。
2.一般建設業の専任技術者要件に該当+元請としての4,500万円以上の「板金工事」について2年以上指導監督的な実務経験がある
この要件を満たしていることの証明に以下の書類が必要です。
・①一般建設業の専任技術者の要件を満たしていることを証明する書類+②指導監督的な実務経験があることを証明する書類(厚生年金被保険者記録照会回答票+建設業許可通知書の写し 等)
専任技術者について更に詳しく知りたい方は「専任技術者とは?」をご覧ください。
条件③ 財産的基礎がある
財産的基礎の要件は、一般建設業許可を取るのか特定建設業許可を取るのかによって違います。
以下にそれぞれの場合に分けて解説します。(一般と特定の違いについて知りたい方は「特定建設業許可と一般建設業許可の違いをわかりやすく解説 」をご覧ください)
<一般建設業許可の場合>
申請時において次の1,2のいずれかに該当する必要があります。
1.自己資本の額が500万円以上である
2.500万円以上の資金を調達する能力がある
以下にそれぞれの要件について解説していきます。
1.自己資本の額が500万円以上である
「自己資本」とは、法人の場合は、賃借対照表における「純資産合計の額」を、個人の場合は、賃借対照表における「期首資本+事業主借+事業主利益-事業主貸+引当金+準備金」をいいます。
2.500万円以上の資金を調達する能力がある
取引金融機関から500万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいいます。
一般建設業許可の財産的基礎等について更に詳しく知りたい方は「建設業許可は500万円ないと取れない?」をご覧ください。
<特定建設業許可の場合>
申請時において次の1~4のすべてに該当する必要があります。
1.自己資本の額が500万円以上である
2.500万円以上の資金を調達する能力がある
以下にそれぞれの要件について解説していきます。
1.資本金の額が2,000万以上である
「資本金」とは、法人の場合は、賃借対照表における「資本金の額」を、個人の場合、貸借対照表における「期首資本」をいいます。
2.自己資本の額が4,000万円以上である
「自己資本」とは、法人の場合は、賃借対照表における「純資産合計の額」を、個人の場合は、賃借対照表における「期首資本+事業主借+事業主利益-事業主貸+引当金+準備金」をいいます。
3.流動比率が75%以上である
流動比率は、貸借対照表における「流動資産合計」が「流動負債合計」より多い場合は計算不要です。
「流動比率(%)=流動資産合計÷流動負債合計×100」で求めます。
4.欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
貸借対照表における「繰越利益剰余金」がプラスの場合や、「資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額」が「繰越利益剰余金のマイナスの額」を上回っている場合は計算不要です。
・法人⇒「資本金に対する欠損の額の割合(%)=(マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金))÷資本金×100」で求めます
・個人⇒「期首資本金に対する欠損の額の割合(%)=(事業主損失+事業主借-事業主貸)÷期首資本金×100」で求めます
条件④ 適切な社会保険に加入している
適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険に加入していなければなりません。
社会保険加入の基本的な考え方は以下のとおりです。
<健康保険・厚生年金保険>
・法人⇒従業員数にかかわらず、加入が必要(役員しかいない場合も加入する)
・個人⇒常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要(事業主本人は加入できない)
<雇用保険>
法人・個人関係なく、次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業者は加入手続きが必要です(法人の役員や個人事業主は加入しません)。
(ア)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ)1週間の所定労働時間が20時間以上である
社会保険について更に詳しく知りたい方は「建設業の社会保険についてわかりやすく解説 」をご覧ください。
条件⑤ 請負契約に関して誠実性がある
法人の場合はその法人、役員等(取締役・相談役・顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
ここでいう「不正な行為」「不誠実な行為」とは、次のような行為をいいます。
・「不正な行為」⇒請負契約の締結または履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
・「不誠実な行為」⇒工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
条件⑥ 欠格要件に該当しない
以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
(1)許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
(2)法人の場合はその法人、役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、個人の場合には本人又は支配人等が次の要件に該当しているとき
ア 精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない者又は破産者で復権を得ない者
イ 建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
ウ 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
オ 営業停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
キ 一定の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ク 暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。
ここまで「板金工事業」の建設業許可を取るための条件について解説してきましたが、6つの条件全てクリアできましたか?
全てクリアできた方は「板金工事業」の建設業許可が取れる可能性がかなり高いです。
次章はいよいよ「板金工事業」の建設業許可の申請手続きについて解説していきます。
「板金工事業」の建設業許可の申請手続き
申請の流れ
申請する役所の「建設業許可申請の手引き」と「建設業許可申請の様式一式」を入手する
申請する役所のホームページからダウンロードするか、窓口で購入します。
手引きを見て建設業許可取得の条件を満たしているか再確認してください。
事前に申請窓口に相談に行くのもよいでしょう。
↓
添付書類の収集
建設業許可の申請には、申請書類の提出だけではなく、許可取得の条件を満たしていることを証明する書類の添付が必要です。
添付書類には、自身が保管している書類と公的機関等で取得する書類があります。手引きの必要書類の一覧表を見て揃えましょう。
添付書類について詳しく知りたい方は「【建設業許可申請】法人の必要書類ガイド」、「【建設業許可申請】個人事業主の必要書類ガイド」をご覧ください。
↓
申請書類の作成
申請書類はケースにより違いはありますが約20種類です。
↓
申請
申請書一式・添付書類・申請手数料を持参して申請します。
申請先によっては予約が必要な場合もあるので確認しましょう。
↓
許可取得
建設業許可通知書が事業所に郵送されます。
申請から許可取得まで知事許可でおよそ1~2か月くらい、大臣許可でおよそ3か月くらいかかります。
※申請書類の作成と添付書類の収集にかなりの時間と手間がかかるので、行政書士に依頼される方も多いです。
申請費用・申請窓口
<申請費用>
知事許可は申請手数料として9万円(新規申請の場合)、大臣許可は登録免許税として15万円(新規申請の場合)が必要です。
<申請窓口>
全ての営業所が1つの県にある場合には、都道府県知事許可、営業所が2つ以上の県にある場合には、国土交通大臣許可を取ります。
| 都道府県名 | 主管課 | 都道府県名 | 主管課 |
| 北海道 | 建設部建設政策局建設管理課 | 滋賀県 | 土木交通部監理課 |
| 青森県 | 県土整備部監理課 | 京都府 | 建設交通部指導検査課 |
| 岩手県 | 県土整備部建設技術振興課 | 大阪府 | 住宅まちづくり部建築振興課 |
| 宮城県 | 土木部事業管理課 | 兵庫県 | 県土整備部県土企画局総務課建設業室 |
| 秋田県 | 建設部建設政策課 | 奈良県 | 県土マネジメント部建設業・契約管理課 |
| 山形県 | 県土整備部建設企画課 | 和歌山県 | 県土整備部県土整備政策局技術調査課 |
| 福島県 | 土木部技術管理課建設産業室 | 鳥取県 | 県土整備部県土総務課 |
| 茨城県 | 土木部監理課 | 島根県 | 土木部土木総務課建設産業対策室 |
| 栃木県 | 県土整備部監理課 | 岡山県 | 土木部監理課建設業班 |
| 群馬県 | 県土整備部建設企画課 | 広島県 | 土木建築局建設産業課建設業グループ |
| 埼玉県 | 県土整備部建設管理課 | 山口県 | 土木建築部監理課建設業班 |
| 千葉県 | 県土整備部建設・不動産業課建設業班 | 徳島県 | 県土整備部建設管理課 |
| 東京都 | 都市整備局市街地建築部建設業課 | 香川県 | 土木部土木監理課契約・建設業グループ |
| 神奈川県 | 県土整備局事業管理部建設業課 | 愛媛県 | 土木部土木管理局土木管理課 |
| 新潟県 | 土木部監理課建設業室 | 高知県 | 土木部土木政策課 |
| 山梨県 | 県土整備部県土整備総務課建設業対策室 | 福岡県 | 建築都市部建築指導課 |
| 長野県 | 建設部建設政策課建設業係 | 佐賀県 | 県土整備部建設・技術課 |
| 富山県 | 土木部建設技術企画課 | 長崎県 | 土木部監理課 |
| 石川県 | 土木部監理課建設業振興グループ | 熊本県 | 土木部監理課 |
| 岐阜県 | 県土整備部技術検査課 | 大分県 | 土木建築部土木建築企画課 |
| 静岡県 | 交通基盤部建設業課 | 宮崎県 | 県土整備部管理課 |
| 愛知県 | 都市整備局都市基盤部都市総務課 | 鹿児島県 | 土木部監理課 |
| 三重県 | 県土整備部建設業課 | 沖縄県 | 土木建築部技術・建設業課 |
| 福井県 | 土木部土木管理課 | - | - |
| 地方整備局名 | 担当部課等名 | 管轄区域 |
| 北海道開発局 | 事業振興部建設産業課 | 北海道 |
| 東北地方整備局 | 建政部建設産業課 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東地方整備局 | 建政部建設産業第一課 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県 |
| 北陸地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 新潟県、富山県、石川県 |
| 中部地方整備局 | 建政部建設産業課 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
| 近畿地方整備局 | 建政部建設産業第一課 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国地方整備局 | 建政部計画・建設産業課 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 九州地方整備局 | 建政部建設産業課 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 沖縄総合事務局 | 開発建設部建設産業・地方整備課 | 沖縄県 |